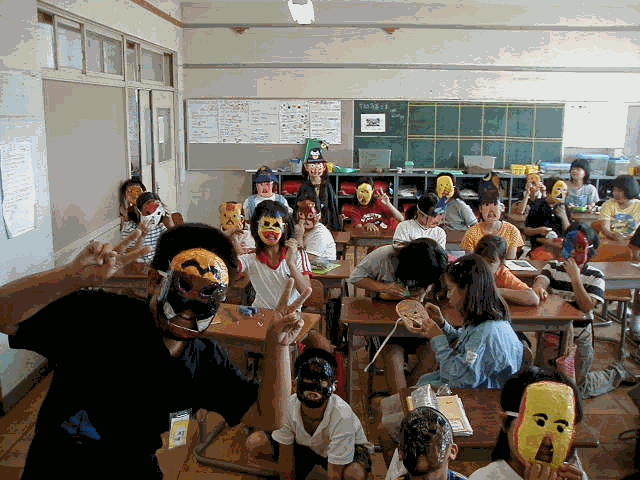
岐阜生研 1999年度 基調提案
「学校を交響的・公共空間として創造しよう」
2.「教育相談」から集団づくりへ~昨年度の岐阜生研の実践が示す方向
昨年度の基調提案の冒頭である。
「昨年度は日本の社会全体を震撼させるような事件が続発し、我々教育に携わる者の認識や生き方が問われたのは当然としても、それに留まることなくこの社会全体の進み往きに根本的な反省を促すものとなった。その代表的な例が神戸の連続小学生殺傷事件、栃木の女教師刺殺事件であろう。これらの事件は、現代における子ども・生徒の対他関係の中に孤立化と権力化、閉塞化が一層進み、それからくる苦悩、不安、精神的外傷が以前にもまして深まっていることの証とみることができる。」
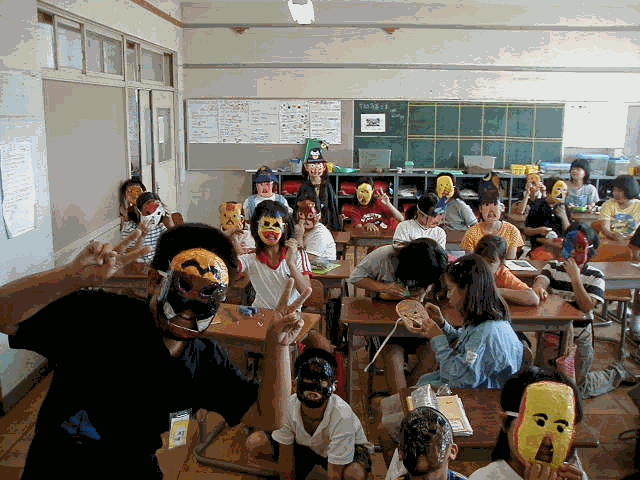
突出した事件の後にきたものは、「学級(学校)崩壊」の旋風であった。「新しい学力観」で指導放棄と新自由主義を振りまいてきた文部省が、異常な刑事事件に慌てて「心の教育」と「道徳教育」のさらなる推進をまたもや通達した結果がこの有様である。小学校低学年から授業が成立しない、絶え間のない私語、立ち歩き、奇声を上げる、隣の子を突然殴る・蹴る。それを教師が咎めたり制止すると、罵倒する言葉が飛んでくる。物が飛ぶ、机の上を跳び回る、教室から飛び出していく。もうまさに何でもアリの状況が全国いたるところで起き始めている。
中学では、小学校段階で「分からぬのも個性」ということで、学習面で遺棄されてきた子どもたちが1・2年で悲鳴を上げる。3年では進路選択で、不況のために経済的負担の大きい私立高校は敬遠され、公立一本組が増加した。そのため公立高校の志望者数が、かつてない異常な倍率を示した。結局は公立高校を不合格になった生徒が前例のない数に上り、この不況で就職先もないのである。この4月から学ぶことも働くこともできないまま社会に放り出された中卒未成年者が巷に溢れているのである。
また1999年1月に総理府から発表された数字によれば、97年度の全国の高校中途退学者数は11万1千人を超えて、中退率は2.6パーセントに上り、82年の調査開始以来最高を毎年更新し続けている。
これら社会的に遺棄された中卒未成年者や高校中途退学者の周囲に責任ある大人の姿はない。そしてその社会的に遺棄された未成年者たちが非行問題行動に墜ちていく・・・その状況に対して、遺棄した大人の側に少年法の改正、すなわち厳罰をもって対処すべきなどという者が存在していることが二重の恥辱と崩壊感を生み出している。今、彼等のそばに、責任ある大人たちがいないことの方が問題なのである。
この事態に、さまざまな見方や意見があるが、その特徴的なものの一つは東大卒の某現役中学教師による著書「学校崩壊」に端的に表れている。かの著者は「正しい管理教育を標榜」し、「これらの学校崩壊という事態は教師の権威(力)が失墜したことによる。だから教師の権威(力)回復こそ急務」と主張しているようである。それらの教師の中には体罰を積極的に肯定する者まで現れてきている。
しかし本当にそうだろうか。栃木の女教師が刺されたのは、その教師に権威がなかったからだろうか。
現代社会に生きる誰もが感じている閉塞感、先行きの不透明感、社会そのものの持つ支配と権力構造。そんなものに対して子ども・生徒は、成長途上で傷つきやすく、弱いがために何よりも敏感に反応する。しだいに希薄になっていく他者の存在、連帯の感覚、深まる孤立感と何かによる抑圧感。そしてそれらの否定的な感覚の中で強まっていく自己の不全感、さらには近未来の自己と他者への恐怖。それらの自己の隅々に偏在する否定的な感情が自分を絶えず内側から攻撃してくる恐怖と傷み。日毎に強まる心的外傷と身体・臓器表出、あるいは行動化。
こんな子どもたちに学校・教師はどのような態度をとったのか。「心の教育」・「道徳教育」は権力構造の上位にある者にとっては重要であろう「思いやり」「勤労奉仕」「規則尊重」「寛容協力」などについては声高に叫び続けてきたが、「理不尽なものへの怒りはどのように表現するか」「不満はどのように表現するか」「異議申し立てはどのようにしたらよいか」「決まり・規則はどのように改廃したらよいか」「意見表明の権利行使の方法はどのようにするのか」「否定的な自己や他者とどのように和解したらよいか」など、民主的な集団や社会にとって必要な内容を教えてきたのだろうか。
唯一手だてとしてとられたのは「教育相談」であった。これはたしかに、不安や悩みを抱えた子ども生徒の声に耳を傾けるということでは重要ではあった。しかし子ども・生徒の不安とは、そのほとんどが自己の内部と外部の民主的・共同的な関係構築を課題としているのに、ほとんどはそれが子どもの精神の内部処理的に終始していることからすると、本質的な解決の方向を示すとは思えないのである。
つまり端的に言えば、弱い者、傷ついた者には教育相談的に癒しを、荒れる者には管理的に権力をもって弾圧を、という分裂した対応では、現代の子どもの抱える諸葛藤を外へ開き、克服をはかっていくことはできないであろう。
「窮鼠猫を咬む」という表現があるように、子どもたちはこの痛々しい状況の中で制度化された儀式ではなく、自前の「カーニバル」を求めたのではなかったか。「カーニバル(祝祭)」は「セレモニー(儀式)」とは異なる。セレモニーが制度的、権力的、儀式的であるのに対して、カーニバルは同時性をもち、主体と客体、「見る・見られる」の境界がなく、制度的・儀式的というより「馬鹿騒ぎ」的であるという意味で、権力者の主催する垂直的な式典でなく、対等平等な民衆の側の祝祭なのである。意見表明や異議申し立ての権利としての表現の仕方も、怒りの表現の仕方すらも、そして同じ思いを共有すべき仲間と連帯を深める方法も、学校や大人によって教えられなかった子どもたちは、爆発的なカーニバルによって、この閉塞的で支配的な世界をまるごと自分ごと、ひっくり返そうとしてみたのではなかったか。閉塞感の中での混乱や崩壊は、むしろ爽快ですらあったのではないだろうか。そのカーニバルさえ抑え込まれた時に、子どもの情念が悲しい事件を引き起こしたのである。
しかし、だからといって学級崩壊という現実をそのままにはできない。たしかに学級崩壊にはカーニバルとしての側面はあるものの、依然として子どもの対他関係は閉塞的、権力的であり、自分と他者、自己とが敵対せざるをえない状況にあるからである。カーニバルによって現実をひっくり返してみたところで、自分や他者との和解と連帯を見通すことのできる地平は一向に見えてはこないのである。そういう意味では、子どもたちは権力的・暴力的な自己と他者との関係の中で、救済を求めて悲鳴を上げているといっていいだろうと思うのである。
そうだとすれば、彼等のことごとく孤立化、私事化された周囲との関係を、社会化・公共化していく技と力を形成していくものとしての政治教育、すなわち集団づくりこそ必要とされるのであろう。
2.「教育相談」から集団づくりへ~昨年度の岐阜生研の実践が示す方向
昨年度の岐阜生研の実践では、桂川氏が「ハルキというパニックを起こす子の指導」という実践を提起した。
この実践は、葛藤し、傷ついている子どもの「癒し」をテーマとしながらも、いわゆる教育相談的カウンセリング実践を乗り越え、仲間との排他的な葛藤関係から民主的・共同的な関係を創り出していったという、集団づくりとして実践されているところにその特徴的実践主題がある。
自己否定感が強く、内的葛藤の強いハルキという子どもは、「しきりに目をしばたたかせる」などのチック的な身体症状を示せば教育相談的なカウンセリングの対象であり、「授業中は少しも落ち着かない」「サッカーで他の子が失敗すると怒りだし暴力を振るう」という場面では弾圧の対象になりがちである。しかし桂川氏は実践的に別の方法をとる。
①子ども分析がある。~彼をめぐる対他関係への着眼
これがなければ指導は管理に終始する。しかもこの分析とは、その子どもの個人的な資質、能力、身体的、家庭的、性格的などの特徴を総ざらいに列挙することではない。その子どもの示す荒れ、身体症状、問題行動として出てきている内的葛藤の要因となる、彼をめぐる対他関係のどこにどのような問題が存在するのかを共有するために必要なのである。そしてそこから集団づくりの指導構想・方針が生まれてくる。桂川氏はハルキの荒れの根元を、わがままや彼の個人的な資質の問題とはみていないので、話を聞いてやって内部処理的にハルキの問題を解決しようとはしなかったのである。
②指導構想・方針がある。~問題を止揚する指導としての仮説
ハルキの問題とは内部処理の問題ではない。したがって桂川氏は重層的な指導構想をもつにいたる。
つまり問題を引き起こしている要因が幾層にも渡っているためである。
一つはハルキ本人への教師の個人指導、アプローチである。これは「ロケットジャンプ」に代表される、ハルキの硬直化している対他関係を柔軟化し、かつ自己を受容し外部に開いていくために必要な指導であった。いわゆる縦糸としての指導である。
二つ目は、学級のリーダーや集団に対する指導である。いわば教育的な集団を創り出す横糸の指導である。ハルキの問題とは、現代の社会や集団、学級、その中の個に遍在する問題でもある。したがってハルキとリーダーや学級集団がいかに共同的に出会うようにするか、その中で競争的・支配的・権力的か、あるいは孤立的・排他的な相互の関係性を民主的共同的なそれに組み替えていくということが実践的に重要なのである。これこそが今日の政治教育として重要なテーマとなる。物語の中でハルキが「喧嘩の回数が減った。作戦を考えたからだ」と言っているのは、この実践がハルキの共同的な対他関係を創り出す上で有効であったことを彼自身が証言しているとみることができる。
三つ目は家庭・母親へのアプローチである。このような問題行動を表現しているのを「ヘルプ」、すなわち救済を求める姿であると認識し、その対他関係性のどこが炎症を起こしているのかを桂川氏はみていこうとする。それは学校における仲間との関係であるだけでなく、多くの場合ミクロ・ポリティクス(個人的な人間関係に集中的に現れる封建的な権力関係)としての家庭内力動システム(端的には家庭内の濃密な関係が「怒り」として集積した関係性)が、その中の母親や子どもという弱い存在に働く場合に、強い内的葛藤として現れることがある。学校で問題行動を示す子どもは、実はこの自分の外側の葛藤を自己内部に取り込んで悩んでいる場合が多い。そしてそのことで家庭の力が集積している母親も悩んでいることが多いのに、学校や教師はその問題に共同的に取り組む態度に欠けるために(本来は家庭を責める気持ちや考えはないにしても)、結果としてその子どもや母親をますます追いつめ、関係を悪化させることが多い。
その意味では桂川氏は、ハルキの問題を克服するには、学校でのハルキへの指導だけでなく、母親と共同的な取り組みを進めていくことが重要であることを見抜き、結果的に母親の自己・対他関係を組み替えることでハルキの問題を克服していく手がかりを得ることができたと言えよう。
③実践から教訓や理論を検証し、新たな実践の発展や課題を生み出す。
ただこの桂川氏の実践では、レポートの長さや切り取り方の問題もあって、リーダーや集団への指導の具体的な部分が分かりづらいという点があったように思える。今後の実践でリーダー・集団への指導をさらに具体的に豊かなものにすべく検証していく必要がある。

また秋の合宿研での粥川氏の実践、常任合宿研での上村氏の実践も教訓的で今後の実践の方向を示すものであったといえる。共通しているのは、両氏の教師として対象となる子ども生徒との権力的でない、共同的なスタンスである。
今、子どもたちが人間と人間、集団と人間との関係に働く力学に際限のない緊張を強いられている。民主的で良心的な教師はそんな子どもと横並びになって対応しようとするが、自治的な活動経験の少ない、そして徹底して私事化された心身をもつ子どもたちは、本来水平的な関係にある者との関係にまで、力学的な関係を持ち込んでしまう。
例えば「規律」が民主的な集団に必要なものであっても、それを窮屈で自らの自由を束縛するものと捉え、その公共性を排撃し始めるのである。かつての校内暴力としての垂直暴力がいじめという水平暴力に、そしてそれが学級崩壊へとつながっていくのである。そしてこういう状況の中で、再び学校・学級に「上からの秩序」を取り戻すための効率的な管理主義、正義の力としての体罰教師容認論が大きな顔をして、学校現場や父母の中にまで登場してくるのである。
しかしその方向では、かつてそうであったように、学校・教師と子ども・生徒、地域・父母が分裂し結果として学校の権力化と子ども・生徒・父母の反発に行き着くであろう。
さらに昨年度の基調提案はいう。
「今後の対応には予測として二つの流れが考えられる。ひとつは新たなる管理主義と「心の教育」が表裏のセットで強化される方向である。すでにナイフ事件にかかわって、その危機感から何人かの校長が学校説明会で「これまで以上にいっそう道徳教育を推進する」という一方で「持ち物検査を実施する」「非行問題行動を起こす生徒はうちの学校へくるな。」などと矛盾した内容を公言している事実がそれを示している。しかもこの流れは、問題行動を管理と「心の教育」で押さえ込んだ後に、上からの力技による一大教育改革という濁流を呼び込むことが考えられる。もはや小手先の改革では、垂直構造下の現在の学校と学びの荒廃に歯止めがかからないことがはっきりするや、それを口実にした改革に乗り出す。それは先の経済同友会の合校構想をひとつのモデルとした、教育と学校の公共性の破壊をもたらすものとなる危険がある。」
この大混乱をもたらす「濁流」の予測は刻々と現実のものとなりつつある。この現代の教育崩壊といってもよい状況の中で、荒れを口実として公教育の解体と民間への払い下げ、そして合校構想の実現に道を開く危険な状況が生まれてきている。新指導要領は2002年度より、いわゆる「総合的な学習の時間」の導入を指示している。これについては昨年度から岐阜生研も針鼠のように警戒心を募らせてきたが、移行措置は今年度あたりから導入されるであろう。学びとはもともと個々の授業で得たものを総合していくものではなかったのか。その内容は環境、福祉、平和、情報、国際理解など地域や学校の特色、実体によって創造的に設定するものとなっている。その内容や目的、実体がはっきりせず、教科、道徳とは別物のそれを教科書なしに週3時間程度、年間100時間以上実施せよというのである。通学区域の弾力化が一部で先行実施されていることから、この「総合的な学習の時間」でどんな内容やカリキュラム、実践をもっているかによって、親が学校を選択してくることもありうる。事実、早期教育の観点から小学校段階で、この時間に英会話を多く実施する学校を選ぼうとする親の意見があるそうである。
週一時間の道徳の時間は、扱いに困った挙げ句に、現実には学活やその他の時間に転用されることが多いが、年間100時間以上実施の「総合的学習の時間」はそうはいかない。道徳や選択教科はそのままで、教科書なしで地域や学校で工夫して勝手にやれというのであるから、まさに新自由主義的なその無責任さにあきれるばかりである。荒れている、荒れる傾向にある学校では、当然のようにますます学校秩序は滅茶苦茶になる。そのことに現場は戦々恐々としている。おそらく先行実践や移行措置として、学校五日制完全実施をにらんで現行土曜日か金曜日の午後あたりにまとめ取りをし、行事(の計画や準備)、集会、奉仕・福祉活動、フィールドワーク等を計画してくる学校が増えるのではないかと思われる。
しかし我々生活指導教師のスタンスとして、子ども・生徒の「学びからの撤退」と「総合的な学習の時間」に関わって予想される混乱にどのような態度や実践ができるのだろうか。それが押しつけボランティアや見かけ上の選択制による好き勝手なことをさせる時間になったり、学校の権力化をいっそう補強するものとして働く危険もある。その反動として子ども・生徒はますます公共空間としての学校から実質的に撤退し、私事化し、他者や集団との関係は空洞化していく。反対に子ども・生徒の参加と自治と学びを具体的に発展させる、学校の公共性を拡大する方向での「総合学習」としての実践がどの程度可能となるのだろうか。移行の動きを監視しながら考えていきたい。
今、教師は子どもの前に権力的な他者としてではなく、共同する他者、彼の存在を照らし出す交響する他者として登場し、その上で学校を公共空間として再生していく自治的活動の実践が期待されるのである。現代の閉塞状況とは、端的に云えばすなわち人間関係のそれである。自分を映し出す鏡としての他者が存在しない。現代において他者とは、自分を抑圧・支配しようとする、あるいはその逆の対象であり、そうでなければ毎日会っていても出逢いのない、実質的に存在しないのと同等の希薄なものになっている。自己の外から自分を脅かす凶暴なもののまなざしを感じ、同時に自己の内側から自他を嫌悪し迫害する力が身体の不和・不協和音を日常的に生み出す。それを互いに警戒・恐怖することなく安心して相互にぶつかりあい、影響を及ぼしあう存在としての他者、そんな集団を渇望している子どもたちなのではないか。桂川氏の実践の中でのハルキは、ある意味で同時代を生きる子どもの代表であろう。もしそうだとすれば、自己や他者と和解し、自他を尊びながら出逢い交わる、心身を通して交響することのできる身体づくりを、まずは教師と子どもとの対話交流や子ども主体の自治的カーニバルの実践の中で追求できるのではないだろうか。
(細江 剛:「飼育祭りに取り組んで」)
また同時に教育的管理の問題も実践的に避けては通れないのを感じる。自治的な活動の結果として、民主的な集団づくりをめざす以上、集団の一つの要素として管理は存在する。そして集団の管理権がどこにどのように存在しているかが問題なのである。集団自身による自治・自覚的規律へと発展を構想するものなのか、あるいは管理統制に終始するものなのか・・・。またそれは今日の学級集団の中にどのように構造的に位置づけられるものなのだろうか。学級崩壊のような状況を前にしてあまり意識的にではないのしても、そのことで悩みながら、具体的な指針となる実践提起を待っている若い教師は少なくないと思われる。いずれにしても、今日的な意味での教育的管理の問題を実践的に研究していきたい。
1999.6.26 文責 田中 秀樹